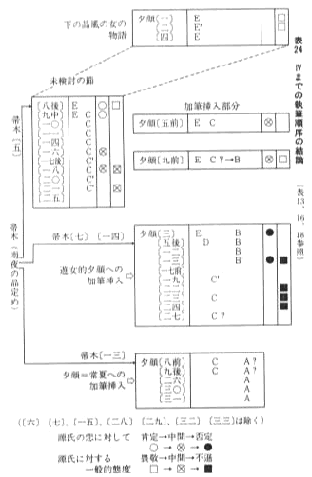
〔三〕で更に問題としなければならないのは「ありつる扇御覧ずれば」である。〔一〕で女童が白い扇をさし出し、夕顔の花をその上に置いて源氏に手渡したのであるから、もし和歌があるとすればその時気付くであろうし、わざわざ「惟光に紙燭召して」見たのだから、書いてあったことを源氏は知っていたはずである。とすれば返歌はすぐ行われてしかるべきであろう。それが当時の貴族階級の習わしであった。この意味でも夕顔〔三〕の位置は不自然である。
それに、現在この女に名付けられている夕顔という名称は〔一〕の白い扇の上に乗った夕顔や、夕顔の咲く宿から命名されたと考えられるが、「心あてにそれかとぞ見る白露のひかりそへたる夕顔の花」(夕顔〔三〕)から命名されたとすると、この夕顔は光源氏のことであるから、やや筋違いな面を含み不自然である。また、いたくわずらいたる乳母への訪問なのに、話が宮仕人の方に行きすぎている。惟光が出て来るまでの間、夕顔を一ふさ折った程度のたわむれの話にしてはおもむきが違っている。
次は惟光の態度である。源氏の問いに対して、「例のうるさき御心とは思へども」とかなり源氏の遊びについては批判的である。この態度は、夕顔〔一〕の「『らうがはしき大路に立ちおはしまして』と、かしこまり申す」という惟光の態度とは異なる。
いったい惟光は源氏のこのような恋にいかなる態度を示しているのであろうか。惟光は桐壺、帚木、空蝉と続く巻までは登場せず、夕顔〔一〕で初めて登場する。にもかかわらず夕顔〔三〕で源氏の恋に対して批判的な態度を示すのである。惟光はたかが乳母の子であり、源氏の家臣、随身である。このような態度がとれるのであろうか。初出から間もない〔三〕で主人に対して批判的なのは不自然すぎる。
夕顔〔三〕で更に特徴的なことは、光源氏と夕顔がゲームを行っていることである。夕顔が正体をみきわめたのですよと詠めば、源氏は寄ってみなければわかりませんよと返歌している。
心あてにそれかとぞ見る白露のひかりそへたる夕顔の花(夕顔)
寄りてこそそれかとも見めたそがれにほのぼの見つる花の夕顔(源氏)
夕顔は光源氏と「思ひあてられ」るので「さしおどろか」せ、源氏はそれに対して「かくわざとめかし」て、返歌したのである。
以上で遊女的な夕顔、源氏の恋に対して批判的は惟光、正体推測ゲーム、が筋立ての上で同一時期と考えられる。
ここで、惟光の源氏の恋にたいする思いや態度が書かれている部分を比較し、更に源氏の行為に対していかなる態度をとったかを検討する(表17)。
惟光は夕顔〔三〕〔一三〕〔二二〕では批判・否定的であり、〔一〕〔二〕〔五前〕〔八前〕
〔八後〕〔九中〕〔一六〕〔一八〕〔二一〕などでは肯定的である。詳細にみると、〔三〕の「例のうるさき御心とは思へども、さは申さで」と、〔一三〕の「わがいとよく思ひ寄りぬべかりしことを、ゆづり聞えて、心ひろさよ」と、〔二二〕の「いとたいだいしき事とは思へど、『さ思されむは』」とは全く同一の書き方で、源氏に対する批判と不遜な態度とは同一時期でであると考えられる。すなわち〔三〕と〔二二〕〔二三〕〔二四〕とは同時期の執筆となる。
恋に対する肯定と畏敬の念、恋に肯定的ではあるが否定が少し含まれ、源氏に助言している部分、恋に対する批判と行為に対する批判、不遜な態度は、源氏と惟光の関係では同じとみてよい。これを
表17 惟光の源氏の恋に対する態度
|
|
|
対して |
態度 |
|---|---|---|---|
|
|
「らうがはしき大路に立ちおはしまして」と、かしこまり申す |
|
|
|
|
かくおはしましたるよろこびを、またなき事にかしこまる |
|
|
|
|
例のうるさき御心とは思へども |
|
|
|
|
すき給はざらむも、なさけなくさうざうしかるべしかし、人のうけ ひかぬ程にてだに、なほさりぬべきあたりの事は、好ましう覚ゆる ものを、と思ひ居り |
|
|
|
|
……など聞ゆれば……いと知らまほしげなる御気色を見て……案内 も残る所なく見給へ置きながら |
|
|
|
|
いささかの事も御心に違はじと思ふに しひておはしまさせそめてけり |
|
|
|
|
わが馬をば奉りて、御供に走りありく 「懸想人のいと物げなき足もとを、見つけられて侍らむ時、からく もあるべきかな」などわぶれど |
|
|
|
|
せめてつれなく知らず顔にて、かけて思ひよらぬ様に、たゆまずあ ざれありけば |
|
|
|
|
わがいとよく思ひ寄りぬべかりしことを、ゆづり聞えて、心ひろさ よなど、めざましう思ひをる |
|
|
|
|
「……仰言もなし、暁に御迎に参るべき由申してなむ……」 |
|
|
|
|
夜中暁といはず、御心に従へるものの、今宵しも侍はで |
|
|
|
|
「……惟光おり立ちて、よろづはものし侍る」 |
|
|
|
|
「何か、ことごとしくすべきにも侍らず」とて立つが……と宣ふを、 いとたいだいしき事とは思へど…「さ思されむは、如何せむ…」 |
|
|
|
|
「夜は明方になり侍りぬらむ。はや帰らせ給ひなむ」と聞ゆれば |
|
もとに肯定→否定、畏敬→不遜・批判を順にならべると、夕顔の変遷がだんだんと明確になってゆく。惟光などの性格は、後期挿入する時期ごとに一つの型を示しており、紫式部の構想がはっきりしてくればくるほど一定化しやすい。前後の関係で動揺することは否めないが、おおまかな執筆順序が浮かび上がってくる。また惟光の態度が一定しない理由は、ある意図をもって後期挿入しているので、そのたびに別の性格付けをしているからである(表18)。
表18 惟光の態度の変遷 (表13参照)
|
|
源氏の恋に対して | 源氏に対する 一般的態度 |
夕顔の類型分類 |
| 夕顔〔一〕 |
|
E | |
| 〔二〕 |
|
E’ | |
| 〔八後〕 |
|
|
E |
| 〔九中〕 |
|
E C | |
| 〔五前〕 |
|
E C | |
| 〔九前〕 |
|
|
E C? →B |
| 〔一六〕 |
|
C | |
| 〔一八〕 |
|
|
C |
| 〔二一〕 |
|
C’ | |
| 〔三〕 |
|
E B | |
| 〔一三〕 |
|
|
B’ |
| 〔二二〕 |
|
||
| 〔二三〕 |
|
C | |
| 〔二四〕 |
|
〔八前〕は夕顔=常夏は除外
〔二四〕は表17に表示できぬが、〔二三〕と同じ態度で
あり不遜になる
夕顔〔五後〕で問題となるのは、「『なほ言ひ寄れ。尋ね寄らでは、さうざうしかりなむ』と宣ふ。かの下が下と、人の思ひ棄てし住なれど、その中にも、思の外に口惜しからぬを見つけたらば、とめづらしく思ほすなりけり」である。明らかに雨夜の品定めを受けている。ところが〔八後〕にも「仮にても、宿れる住の程を思ふに、これこそ、かの人の定めあなづりし下の品ならめ、その中に、思の外にをかしき事もあらば、など思すなりけり」という文章が出てくる。この二つを比較したのが表19である。夕顔のすまい、身分、源氏の思惑など、一見ほとんどよく対応し、差がないと結論しがちであるが、そうなると〔八後〕の文章は重複となってしまう。紫式部がこのような凡庸なことをするはずがない。微細な検討が必要である。
違いは、まず第一に源氏の意志が異なる。第二に源氏は夕顔の宿に対して〔五後〕で「下が下と、人の思ひ棄てし住」と断定しているにもかかわらず、〔八後〕では「宿れる住の程」を「下の品ならめ」と推定しているのである。断定が先で推定が後になるのはおかしい。
〔八後〕では、源氏の恋に対する惟光の態度は、源氏を夕顔の家に「しひておはしまさせそめてけり」と肯定的で、夕顔の性格も下の品風である。〔五後〕は何らかの意図をもって紫式部が後期挿入したのである。それは、夕顔の身分についての断定と推定の違いに着目すべきなのである。
表19 夕顔〔五後〕と〔八後〕の比較
|
|
|
|
|
|
| 五後 | 人の思ひ棄てし住なれど (断定) |
かの下が下と (断定) |
思の外に口惜しからぬ を見つけたらば |
なほ言ひ寄れ (積極的) |
| 八後 | 仮にても、宿れる住の程を 思ふに (推定) |
下の品ならめ (推定) |
思の外にをかしき事も あらば |
……など思すなりけり (消極的) |
夕顔〔五後〕の「下が下」は帚木〔五〕の「下のきざみ」を受けているとも考えられるが、「下のきざみ」であって「下が下」とは断定していないのだからやや無理。帚木〔七〕の「上が上」や帚木〔一四〕の「下が下」を受けたとするほうがよいと考えられる。故に夕顔〔五後〕は帚木〔六〕〜〔一五〕の後である。夕顔〔八後〕の「下の品」の語はせいぜい帚木〔五〕を話の前提として受ければよいから、帚木〔四〕〔五〕→夕顔〔八後〕と考えられる(表20、21)。つまり、雨夜の品定めとの関係
表20 雨夜の品定めと夕顔の類型分類
|
|
|
|
| 帚木〔五〕 | 夕顔〔八後〕 |
|
| 帚木〔七〕〜〔一四〕 | 夕顔〔三〕〔五後〕 |
|
| 帚木〔一三〕 | 夕顔〔九後〕〔二六〕〔三〇〕〔三一〕 |
|
で、夕顔〔五後〕を挿入したと考えたほうがよい。雨夜の品定めも次々と後期挿入されたために、後の夕顔の巻にも挿入を行い、雨夜の品定めとの連続性と、全体的に夕顔との関連性を持たせることを意図したのである。微細な点では凡庸さが生じてしまったが、夕顔〔五後〕を挿入したことによって雨夜の品定めも一体化し、夕顔の巻との関連が密となっている。雨夜の品定めの執筆順と夕顔の類型分類との関係を表示する。雨夜の品定め論は、次巻で詳論する。
表21 執筆時期の対応
| 帚木〔七〕 帚木〔一四〕 |
上が上 下が下 |
夕顔〔五後〕 | 下が下 | 断定 |
| 帚木〔五〕 | 人の品 中の品 三の品 下のきざみ |
夕顔〔八後〕 | 下の品 | 推定 |
夕顔〔一二〕は光源氏が夕顔〔三〕の和歌を受けて自らを明らかにする部分であり、夕顔〔三〕を前提するだけでなく夕顔自体が遊女的である。ここで正体推測ゲームに一応の結論がつく。夕顔〔一三〕は源氏の恋に批判的惟光である。夕顔に対しても積極的に介入を行っている。
〔一〇〕から〔一六〕までの時の経過を考えてみると、〔一二〕〔一三〕が挿入であることがより明らかとなる(表22)。
〔一一〕で「まだ知らぬことなる御旅寝に、息長川と契り給ふことより外のことなし」とあるから
表22 夕顔〔一〇〕から〔一六〕までの時間経過
| 〔一〇〕 | 八月十五夜→暁近く→心安くて明さむ→明方も近うなりにけり→朝の露 |
| 〔一一〕 | いさよふ月→明け行く空→御粥など急ぎ参らせ→御旅寝に、息長川と契り 給ふことより外のことなし |
| 〔一二〕 | 日たくる程に起き給ひて→うらみかつはかたらひ暮し給ふ |
| 〔一三〕 | 惟光尋ね聞えて、御くだものなど参らす |
| 〔一四〕 | 静かなる夕の空をながめ給ひて………添ひ臥し給へり→夕ばえを見交して→ 添ひ暮して |
| 〔一六〕 | 宵過ぐる程すこし寝入り給へるに→風すこしうち吹きたるに、人は少くて、侍 ふ限みな寝たり |
「息長川」「外のことなし」に着目すれば、時間的な感覚として、契っているのは午前中だけではないであろう。ほとんど日中すべてとするのが語感として妥当である。それが〔一二〕で 「日たくる程」に起き、今度は「かたらひ暮」すとなるのでは違和感が生じる。更に〔一三〕で「御くだもの」をいただくとなると、この間の契りは「契り給ふことより外のことなり」ではなくなってしまう。〔一二〕〔一三〕がないほうが、朝から「息長川と契り給ふことより外のことなし」で、「たとしへなく静かなる夕の空をながめ給ひて」〔一四〕となっても何かと「添ひ臥し」ているのではないか。そして〔一六〕の「宵過ぐる程」には「すこし寝入り給へる」となり、すべての言葉が生きる。〔一二〕〔一三〕は内容的にも時の関係からも〔二〇〕〜〔一六〕のなかでは異質であり、後期挿入と考えられる。
〔一五〕では①「内裏にいかに求めさせ給ふらむを」と、②六條わたりのことが語られる。
①は〔二〇〕の「内裏より御使あり。昨日え尋ね出で奉らざりしより」にかかってゆくが、②は〔一五〕以後、夕顔の巻ではどこにも受けるものがない。六條わたりに「うらみられむ」にもかかわらず、その後は通うでもなく、うらみがいかに発展するかもない。仮に、六條わたりが出ている夕顔〔七〕の「つらき御夜がれの寝ざめ寝ざめ、思ししをるる事、いと様々なり」を受けるとすると、〔一五〕以前にこれを受ける部分があってよいはずである。例えば〔八後〕の「しひておはしまさせそめてけり」の初回の契りの時にはまさに六條わたりのことがふっと思いわたるであろうし、また〔九前〕の「いとしばしばおはします」の時の方が六條わたりにとって辛いはずであり、〔一〇〕の「暁近く」にこの思いにかられてもよいはずである。
まさにこの節はとってつけたものであり、①の内裏のことですら〔二〇〕と重複しており、〔一五〕はなくてよいものである。
夕顔〔一六〕からは「いとをかしげなる女」のことが出て来るが、これとても六條わたりと結びつけるなら、六條わたりに似た女とすればもっと鮮明になるはずであるのに明記していない。夕顔が死亡してからでも、「いとをかしげなる女」はおおよそ六條わたりであったことをほのめかしてもよいのに、六條わたりは〔一五〕以後どこにも書かれていない。ではなぜ〔一五〕に六條わたりが突然出て来たのか。それは、夕顔が物の怪にとり殺される部分を書いたあとで、何らかの意図をもって怨念と六條わたりを結びつけるために、〔一五〕があとから挿入されたからと考えられる。
〔一六〕〜〔二五〕の内容は、夕顔が物の怪にとりつかれて怪死し、源氏は二條院へもどり、病気かかっているのにわざわざ死亡した夕顔を野辺おくりしたのち、なんとか源氏が回復するまでである。その中の〔二二〕〜〔二四〕は一連の話で、源氏が無理やり夕顔の死顔を見に行くところである。〔二二〕〜〔二四〕がなくても後半に何の影響も与えないこと。惟光の態度が批判的で不遜であること。この二つの理由から、これは遊女性の時期の挿入である。
〔二五〕で源氏は右近と語るが、〔二二〕〜〔二四〕がなくて問題となるところは、右近が二條院にいないのではないかということである。しかし、「かの右近を召し寄せて」「侍はせ給ふ」のであるから、ここでは右近を二條院に召し寄せてと解釈してよい。そして病が「いささか隙ありて」のとき、右近を「召し寄せて」語るのであるから問題はない。
〔二二〕〜〔二四〕があって困るのは、右近と源氏が語るとき、夕顔の死顔を見に行ったこと、馬からすべり落ちたこと、などの語りが〔二五〕の中にないことであるが、内容からしても〔二二〕〜〔二四〕は〔二五〕にとって、なくても何ら不都合のない節である。すなわち〔二二〕〜〔二四〕は〔二五〕に対し後期挿入である。
さて、〔一六〕〜〔二五〕の間で〔二二〕〜〔二四〕が挿入されたとすると、残りの節でも細かい読みをしなければならない。このあたりの冗長な感じはどこから来ているのであろうか。第一に源氏の病についてである(表23)。第二に惟光の探し方である。この間の執筆順序を決めるのは難しい。
まず〔一七〕の「かの尼君などの聞かむに、おどろおどろしくいふな。かかるありきゆるさぬ人なり」という表現に注目してみる。これと〔二一〕の「少将の命婦などにも聞かすな。尼君ましてかやうの事などいさめらるるを、心はづかしくなむ覚ゆべき」は、同じような表現である。〔二一〕は事件が終わってからであり、〔一七〕は怪死事件の最中である。〔一六〕で怪死した夕顔を見て、源氏は「あが君、生き出で給へ」とあわてふためき、右近は「泣き惑ふ」状況であり、夕顔の死の直後でまだ感情が動揺している時である。〔一七〕でも後半は右近が「君につと添ひ奉りて、わななき死ぬべし」というほど動揺している状況である。このような時に〔一七〕の前半で「かの尼君などの聞かむ
表23 源氏の病の表現 (*は後期挿入部分)
| 夕顔〔一七前〕 | 物宣ふやうなれど、胸は寒りて |
| *〔一七後〕 | われ一人さかしき人にて、思しやる方ぞなきや |
| 〔一八〕 | 君は物も覚え給はず、われかの様にておはし著きたり |
| *〔一九〕 | なやましげに見えさせ給ふ いと苦しく惑はれ給へば、かくはかなくて、われも徒になりぬるなめり |
| 〔二〇〕 | 苦しくて、いと心細く思さるるに しはぶきやみにや侍らむ、頭いと痛くて苦しく侍れば………ただ覚えぬ 穢に触れたる由を奏し給へ。いとこそたいだいしく侍れ 御心地もなやましければ |
| 〔二一〕 | われもいと心地なやましく、いかなるべきにかとなむ覚ゆる |
| *〔二二〕 | 御心地かきくらし、いみじく堪へ難ければ かき乱る心地し給ひて |
| *〔二三〕 | かくいふわが身こそは、生きとまるまじき心地すれ |
| *〔二四〕 | 馬よりすべりおりて、いみじく御心地惑ひければ |
| 〔二五〕 | 臥し給ひぬるままに、いといたく苦しがり給ひて、二三日になりぬるに、 無下に弱るやうにし給ふ 世に長くおはしますまじきにや いささか隙ありて 二十日あまりいと重くわづらひ給ひつれど、ことなる名残のこらず、お こたるさまに見え給ふ あらぬ世によみがへりたるやうに、しばしは覚え給ふ |
| 〔二六〕 | おこたり果て給ひて |
に……ゆるさぬ人なり」という落ち着いた言葉が出るとは思えない。それゆえ〔一七〕の初めから「大方のむくむくしさ譬へむ方なし」までは夕顔〔一七前〕とし、このあとの節とも無関係であり後期挿入である。
〔一五〕の「内裏にいかに求めさせ給ふらむを、何処に尋ぬらむ、と思しやりて……」と、〔一七後〕の「内裏に聞召さむをはじめて、人の思ひいはむ事……をこがましき名をとるべきかな」とは、その中間の〔一六〕で夕顔が死亡しても、全く同一の感情表現である。であるから夕顔〔一七後〕→〔一五〕である。(Ⅳの5参照)
次に〔一九〕と〔二〇〕の源氏の病を比較すると、〔一九〕は「御覧せきあぐる心地し給ふ。御頭もいたく、身も熱き心地して、いと苦しく惑はれ給へば、かくはかなくて、われも徒になりぬるなめり、と思す」である。その一行あとの〔二〇〕では「苦しくて、いと心細く思さるるに」とある。
〔一九〕では「はかなくて、徒になりぬる」のであるから「死ぬ」感じである。しかし〔二〇〕
では「苦しくて心細い」のであって、死ぬまでの感情には至っていない。だからこそ、そのあと頭中将に「いかなる行触にかからせ給ふぞや」と聞かれたりするのでる。「徒になりぬるなめり」ほど重い病なら、自らの病気で参内できぬと上奏したほうがよいのではないかと考えられる。しかし、「覚えぬ穢に触れたる由」で参内できぬと奏しているのである。〔一九〕は不自然である。
更に女房の源氏の病への感想であるが、〔一九〕は「何処よりおはしますにか。なやましげに見えさせ給ふ」である。〔二〇〕は「日高くなれど、起き上り給はねば、人々あやしがりて、御粥などそそのかし聞ゆれど」であり、〔二一〕は「ほの聞く女房など、あやしく何事ならむ、穢ひの由宣ひて、内裏にも参り給はず、またかくささめき歎き給ふ、とほのぼのあやしがる」となっているが、これは〔一九〕の「なやましげに見えさせ給ふ」と矛盾し、その様子を見ていないことになるから〔一九〕はないほうがよい。〔一九〕がなければ〔二〇〕の「人々あやしがりて」が生き、更に〔二一〕へと自然な感情の流れとして続いていく。
やはり〔二〇〕のほうが〔一九〕より先に執筆されたのであろう。〔一九〕は内容的には〔一八〕で源氏が夕顔を見捨てて二條院に帰ってしまったので、夕顔が「生き返りたらむ時、いかなる心地せむ」ということが中心で、〔二二〕〜〔二四〕の野辺おくりの話へと発展させるために後期挿入したのであろう。
次に惟光について考察してみる。
「『惟光の朝臣の来りつらむは』と、問はせ給へば」(〔一六〕)
「惟光の朝臣の宿なる所に罷りて、急ぎ参るべき由いへ、と仰せよ」(〔一七前〕)
「惟光疾く参らなむ、と思す」(〔一七後〕)
「からうじて、惟光の朝臣参れり」(〔一八〕)
「日暮れて惟光参れり」(〔二一〕)
であるから、〔一七前〕が抜けているほうがすっきりする。
あるまじき心の報に、かく来し方行く先の例となりぬべき事はあるなめり、忍ぶとも、世にあること隠なくて、内裏に聞召さむをはじめて、人の思ひいはむ事、よからぬ童べの口ずさびになるべきなめり、ありありて、をこがましき名をとるべきかな、と思しめぐらす」と、かなり詳しく源氏の心情を述べている。
また許されぬ行動をとってしまったことに対する反省という意味では、〔一七前〕の「かかるありきゆるさぬ人なり」は〔一七後〕と重複している。この意味でも〔一七前〕はなくてもよい。〔一七後〕は「しのぶのみだれ」(帚木〔二〕)と同じ次元で、「かかる筋」(夕顔〔九中〕)程度の意味である。しかし、〔一七前〕は明らかに「ゆるさぬ」筋であって、「しのぶのみだれ」程度の行動から離反している。〔一七後〕→〔二一〕→〔一七前〕の執筆順としたほうが自然である。
以上をまとめると執筆時期は三期にわけられ、次のようになる。
夕顔〔一六〕〔一七後〕〔一八〕〔二〇〕〔二一〕〔二五〕
夕顔〔三〕〔一三〕〔一七前〕〔一九〕〔二二〕〔二三〕〔二四〕
夕顔〔一五〕
夕顔〔二五〕〔二六〕〔二七〕であるが、夕顔の素姓を明らかにする夕暮れの語り方から〔二六〕が常夏としての後期挿入であることはⅢで明確にしたが、更に通読してみると違和感はもっと確実なものとなる。すなわち「右近を召し寄せて」(〔二五〕)、「右近を召出でて、のどやかなる夕暮に」(〔二六〕)、「夕暮の静かなるに(右近と語る)」(〔二七〕)と、三回も右近と語る同じパターンが続いていること。また病の点でも「いといたく苦しがり給ひて」→「いささか隙ありて」右近と語り→「二十日あまりいと重くわづらひ給ひつれど、ことなる名残のこらず、おこたるさまに見え給ふ」→「あらぬ世によみがへりたるやうに」(以上〔二五〕)とあり、「おこたり果て給ひて」(〔二六〕)と重複している。
さて〔二七〕であるが、常夏期の挿入である〔二六〕より前に書かれたことは先に明らかにした。ここではその時期がいつであったかを検討する。この節中の「耳かしがましかりし砧の音を、思し出づるさへ恋しくて、『まさに長き夜』とうち誦じて臥し給へり」は〔一〇〕〔一一〕の展開と同様で、〔一一〕の「息長川」の長さ「長き夜」の長は同じ情感である。それ故〔二七〕は〔一〇〕〔一一〕よりあとの執筆である。また〔二七〕の「かの夕顔の宿」は〔三一〕の「かの夕顔の宿」と同一であり、これ以外には使われていないので、常夏挿入に近い時期と推定される。
更に夕顔の紹介がここ(〔二七〕)でも出て来るので、それより前の節の紹介の仕方と比較して考察する。〔二六〕の紹介の仕方についてはすでに述べた。
まず夕顔〔五後〕の「かの下が下と、人の思ひ棄てし住なれど」と比べるとどうであろうか。仮に〔二六〕が〔二七〕より先に書かれたとすると、夕顔は中の品の女と読者の記憶に残ってしまう。そこに〔五後〕が後期挿入されると読者は「おや?」と戸惑うのではないか。その点でも〔二六〕は〔二七〕より後に書かれたと考えたい。〔二七〕には「かの夕顔の宿を思ひ出づるもはづかし」や「耳かしがましかりし砧の音を、思し出づるさへ恋しくて」という住居に関する表現があり、現在のように〔五後〕→〔二七〕と読んでいっても、そういうことも言えると納得されるであろう。身分の点でも〔二七〕はぼかした表現である。それ故〔二七〕は〔五後〕よりも後のほうが挿入時期としてはよい。
〔五前〕と〔二七〕は表現に違和感がなく、どちらが先に書かれたともいえない。
〔三〕とはどうであろうか。〔二七〕を先に読んでいるとなると、「揚名の介」の妻が若やいで、兄弟などが宮仕人として来通っているその「宮仕人ななり」といえるであろうか。後期挿入は現在でこそ順序は前後しているが、当時の読者とすればやはり早く書かれたほう、つまり後方にあるものの記憶が残っているから、前方に挿入されたとしても〔二七〕を前提として〔三〕を読む感じとなる。〔二七〕で父親は三位の君らしく、夕顔は中の品のようだとしたのだから、その記憶がなまなましい時期の後に下の品と断定した〔三〕を挿入するのはむつかしい。従って「宮仕人だろう」と推定した〔三〕を書いた後に〔二七〕を加えたとしたい。
以上から〔二七〕は〔三〕〔五後〕、〔一〇〕〔一一〕の後で〔二六〕の前、すなわち遊女的夕顔の後で常夏の夕顔の前の挿入となる。
ここまでの一応の執筆順は、特別の事情がない限りは現行巻順に読むという原則にしたがって、遊女的夕顔は、
夕顔〔三〕〔五後〕〔一二〕〔一三〕〔一七前〕〔一九〕〔二二〕〔二三〕〔二四〕〔二七
〕
の後期挿入によって形成されたと結論される。全体の執筆順を表24に示す。
さて〔三〕〔一二〕が後期挿入であるならば、夕顔の巻名のことも考えねばならない。現在の巻名の「夕顔」が和歌によって命名されたという通説では、夕顔=常夏を意味するのに対し、和歌では夕顔=源氏であるから論理的でない(「1 夕顔〔三〕の特徴」を参照)。かえって〔三〕が後期挿入であるとする方がより適切である。そうすると現在の巻名の新たな論拠が必要となる。
表24 Ⅳまでの執筆順序の結論
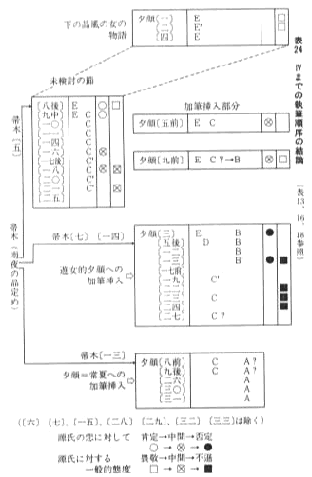
初期の夕顔物語の中に、主人公の女性を夕顔と命名してよい描写がある。それは〔一〕の「白く咲けるをなむ夕顔と申し侍る。花の名は人めきて、かうあやしき垣根になむ、咲き侍りける」と「くちをしの花の契や。一ふさ折りて参れ」である。夕顔の花(女性)に光源氏が興味を持ち、一ふさ折る(女性と関係を持つ)ということであるから、巻名となる女性として自然に夕顔が浮かんでくる。また夕顔の品や源氏との女性関係をも暗示して味わいが深い。序に述べた疑問が氷解するのみでなく、「くちをしの花の契や。一ふさ折りて参れ」という描写が光ると感じるのは私だけであろうか。紫式部の文章力のすばらしさに驚嘆するのみでなく、遊女的夕顔の部分の加筆挿入にあたっても、すでに流布していた巻名を上手に利用し、後期挿入の不自然をなくすたゆみない努力に敬意を表したい。
夕顔〔三〕のように和歌中に「夕顔」を使えば、現在でもそうであるように、夕顔の巻名は〔三〕に由来していると読者は考えてしまうから、〔三〕がもともと夕顔の巻に存在した節であると読者を思い込ませてしまうのである。