| 〜ようこそ沖縄館へ〜 | |
「かりゆし」とは、「嘉例吉」と字を当てることがあります、「海ぞめでたき」です。海は、沖縄の人々のとって古来すばらしいものでした、資源を恵む母であり、文化を運ぶ道でした。
海は時には荒れ、あるいは戦争の道になって島を暗く閉ざす事がありありました。この閉ざされた海を開かれた原点へ戻したいと言う願いを「波の声もとまれ、風の声とまれ」と言う古歌の一節をかりて表現しました。
「海やかりゆし」とは、沖縄文化永遠のテーマです。
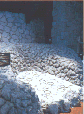
沖縄の古代信仰=ニライ・カナイと御嶽(ウタキ)を表現して沖縄の人々の海への信仰のあり方を現物資料・スライド写真、解説パネル、音声などで紹介しています。
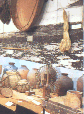
海のかかわりあいの母体となった太古の沖縄の姿は、うかがい知るすべもない。しかし、小さな島の空間だけで暮らしていた頃の人々の生活や心は、おぼろげながらも、考古資料や民族資料の中にそのイメージをたどることが出来ます。

漁労の発達のプロセスを現物資料、カラーコルトン、復元資料などで示し海への信仰に支えられて発達した漁労が、次第に造船技術、航海技術の発達をもたらした過程を明るく描き出します。

14世紀から16世紀までの琉球は、海と深く結びついた琉球人が、最もグローバルに躍動した時代であった。このコーナー では、大交易時代の琉球人の足跡を海外にたどりながら、それらの国々の諸民族の息吹、人間群像、そしてヨーロッパ勢力のアジア進出と琉球交易ルートの変化などを壮大な歴史のドラマとして描写します。
| |
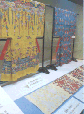
「開かれた海に」にくりひろげられた大交易時代は諸民族との接触、交流を通じて、土着文化の上に異民族文化を吸収しつつ
、ユニークな琉球文化を創り出していった。
このコーナーでは、海の道が招来した琉球の文化財の数々を紹介しています。

1609年、ポルトガル伝来の銃を手にした薩摩島津の軍勢が、突如琉球に侵入した。琉球王国は薩摩島津の支配するところになった。このコーナーでは、薩摩島津が、琉球統治の方針を示した令達書(掟十五条)や「薩摩上国使者」の絵巻などを 紹介しています。

変わりはてた第二次大戦の海を展示すると同時に、その中をたくましく生き抜いてきた人々のドラマを当時の生活用具の中からのぞいて見ましょう。

本県の優れた現代の伝統美術工芸品を随時展示紹介し、又、特別企画展をする他、ギャラリーとしても利用し、多目的に使用されています。
| |